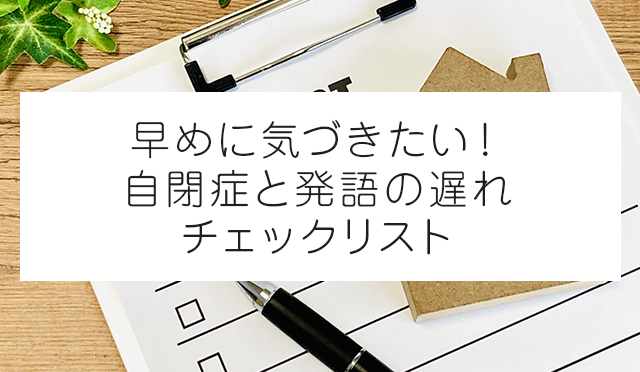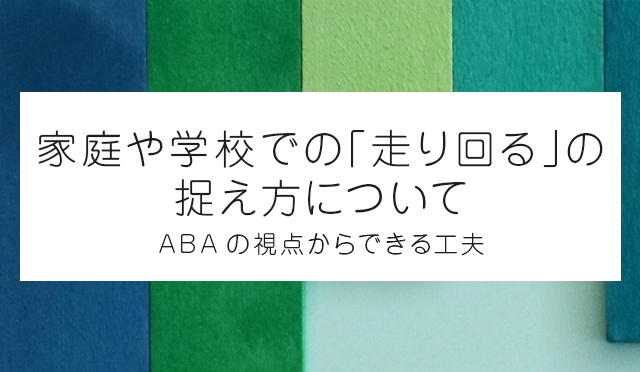脅しは一時的? 長続きしないしつけの理由
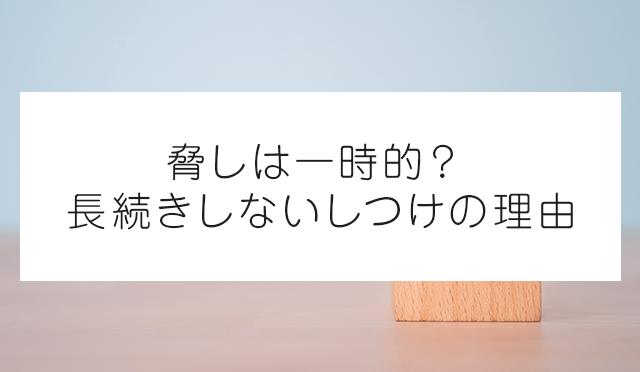
はじめに
その「脅し」、効果は長続きしますか?
弊社の夏休み最終日、私はひとり贅沢にお茶を楽しんでいました。隣の席には、明らかに「ママ友」らしき3人組が、楽しそうにおしゃべりに花を咲かせていました。
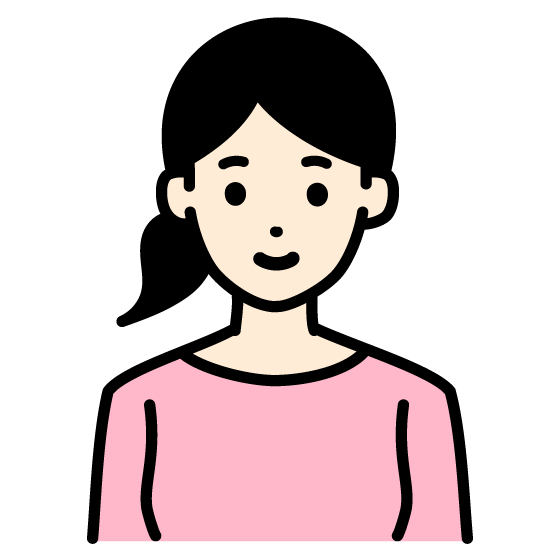 ママA
ママAうちのこ、本当に言うこと聞かないから、「鬼くるで!」というアプリを使ってるのよ
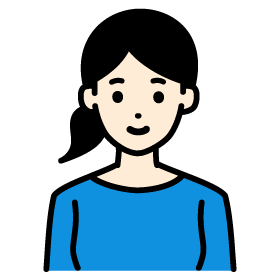 ママB
ママBうちも!あれいいよね!
 ママC
ママCえ、うちは、そんなんしたら警察よびますよ、というと、「ギャー」って叫ぶよ
と大笑いをしていました。
「ごめんなさい、聞こえてしまった!」と心の中でつぶやきながら、慌ててイヤホンを耳に差し込みました。流行りの音楽を流してみたものの、うーん……やっぱり気になってしまい、悶々としてしまいました。
確かに即時的な行動の変化を引き起こすことはあります。けれども、「長期的に見るとあまり望ましい方法とは言えないな」と感じてしまいました。
保護者や先生の間でよく聞かれる声:「○○しないと鬼が来るよ」「○○しないともう知らないよ」
脅しには一時的な効果がありますが、なぜ人は繰り返し使ってしまうのでしょうか。本記事では、脅しが長期的な成長につながらない理由を、ABAの視点から解説していきます。
- 脅しの問題点
- 脅しの代わりにできること
脅しの問題点
発達年齢に合っていない
このママ友さんたちのお子さんは、まだとても小さいのかもしれません。けれども、「鬼はこない」ことには、すぐに気づいてしまうでしょう。小学校低学年以降になれば、「論理的な説明」や「共感的な対話」が求められる時期に入ります。
脅しは「恐怖によるコントロール(行動を抑える方法)」であり、子どもの成長に欠かせない信頼関係を損ねる恐れがあります。さらに、「あ、また嘘を言っているんだ」と子どもが学習してしまう可能性すらあるのです。
子どもは模倣する
子どもたちは、周囲を本当によく観察し、そこから学んでいます。大人の言動は子どもにとって大切なお手本です。たとえば「○○しないと叩くよ」といった脅しを耳にすれば、子ども自身も他の子に対して同じような脅しを使ってしまうかもしれません。その結果、対人スキルが歪むリスクがあります。
一時的な効果しかない
行動分析学の観点から見ると、脅しの最大の問題点は「弱化」です。つまり一時的に行動を減らす効果はあっても、すぐに慣れてしまい効果は薄れていきます。たとえば、このママ友のお子さんは今は「警察」という言葉で泣き止んでいますが、それは本質的に行動が変わったわけではないのです。
自発的な行動が育たない
脅しは長期的な行動改善にはつながりません。それどころか、子どもは「叱られないために動く」ようになり、自発的な行動や自己調整の力が育ちにくくなります。その結果、支援者が不在のときには行動が元に戻ってしまい(般化しない)、「怒られたくないからやる、 大人がいないとやらない」といった、長期的な自己コントロールの発達が阻害されてしまうのです。
学習機会を奪ってしまう
「なぜそれがダメなのか」「どうすればよいのか」といった建設的な学びは、脅しからは生まれません。
「ダメって言ったらダメ!」「鬼がくるよ!」では、子どもは理由を理解できず、建設的な会話の練習や考える力の育成にもつながらないのです。
代わりにできること
脅しを使わない関わり方
では、忙しい毎日のなかで脅しを使わずに、どうやって望ましい行動を増やしていけばよいのでしょうか。
- (1)ルールの明確化と選択肢の提示
-
気になる行動が起きる前に、「〇〇をしたら〇〇ができる」といったルールをはっきりさせておくと効果的です。
- (2)正しい行動をしたときに、すかさず賞賛する
-
「できて当たり前」と思う行動でも、叱るより先に賞賛することが大切です。
- (3)やってしまった行動に注目しすぎない
-
「なんで〇〇したの!」と言いたくなる気持ちはよくわかります。ですが、その言葉がかえってその行動を強化してしまうこともあります。
おわりに
脅しに頼らない関わり方は、時間はかかります。即効性もなく、「してやった!」感がありません。それでも、本来目指している姿に成長させ、長く続く効果をもたらすのです。
どうか、あのママ友のお子さんたちが、脅されることのない新学期を迎えられますように。