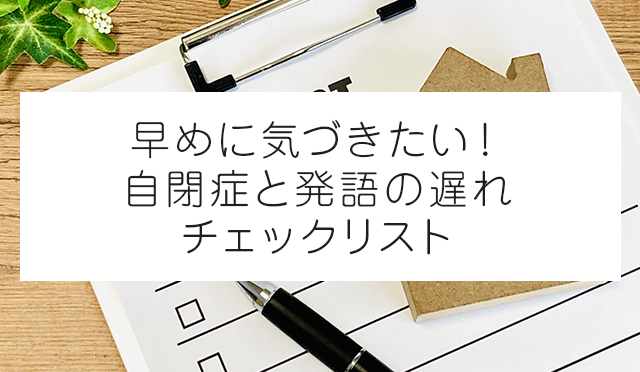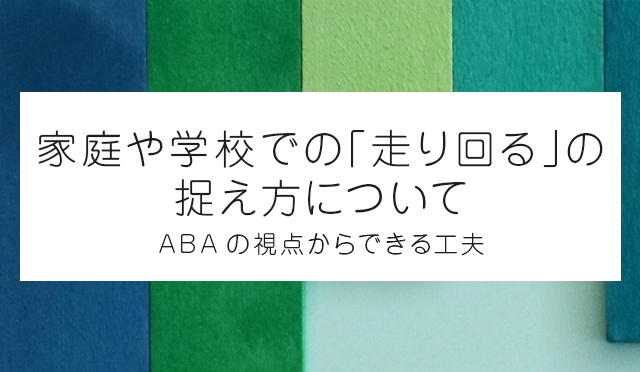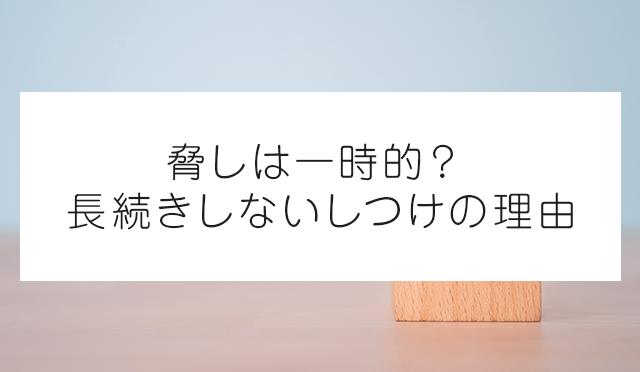子どもの言葉(発語)が遅い原因と発達目安/言葉の発達のために「やってほしいこと」「避けてほしいこと」
子どもは生後9ヶ月~1年6ヶ月ぐらいになると言葉を話し始める子が多く、3歳くらいになると質問をするようになります。子どもが話し始めてもいい時期を過ぎても、まわりの同じ年の子と比べたりして話し始めないと心配になりますよね。
今回は、子どもの「言葉(発語)が遅い原因」と「言葉の発達目安」についてや言葉の発達のために「やってほしいこと」「避けてほしいこと」をご紹介します。
- 発語が遅い子どもの特徴は?
- 子どもの言葉の発達目安
- なぜ言葉の発達が遅れるのか
- 子どもの言葉の発達のために「やってほしいこと」「避けてほしいこと」
できるだけわかりやすく、子どもの言葉が遅い原因や言葉の発達目安、言葉の発達のために「やってほしいこと」「避けてほしいこと」について解説していきます。
発語が遅い子どもの特徴は?

子どもの発語は個人差が大きいため、専門家の正しい診断が必要ですが、以下に一般的な発語が遅い子どもの特徴を挙げます。ただし、必ずしもこれらの特徴がすべて当てはまるわけではありません。
発語が遅い子どもの特徴
- 初期の発語が遅い
- 語彙の成長がゆっくり
- 簡単な文の組み立てが難しい
- 身振り手振りや表情で会話する
通常は1歳半くらいになる頃には言葉を発するようになりますが、発語が遅い子どもは、まだこの時期に言葉を発しません。
言葉を発してもいい頃になっても新しい単語を覚えることができず、語彙が増えないことがあり文法や文章構造に対する理解も遅れています。
文法・文章理解の遅れから、簡単な文を組み立てることが難しく、言葉ではなく表情やジェスチャーなどを通じてコミュニケーションをとることがあり、他の子どもたちとのコミュニケーションをとることや遊びに参加することが難しい場合があります。
子どもの言葉の発達目安

まわりの子どもが言葉を発し始めると、どうしても「自分の子どもは遅れているのでは?」と不安で焦ってしまうことも。
子どもの言葉の発達は、年齢別に知っておくと、過度な不安を抱くこともありません。
以下に言葉の発達目安をご紹介いたします。
【0~1歳前後】喃語(なんご)
喃語(なんご)とは「あー」「ダー」「うー」などの赤ちゃんが発する言葉です。この時期は、基本的な音や音の組み合わせを真似することから始まります。
【1歳から2歳】一語文~二語文
1〜2歳には「わんわん」「わんわん まって」など、一語文や二語文を使い始める時期です。基本的なこちらの指示や要望がわかるようになり、気持ちを表現する力が向上します。
【2歳から3歳】三語文
新しい単語を覚え、語彙が増えていきます。「これなぁに?」と、名前に興味を持ち色々なことを質問する時期です。2〜3語の簡単な文を組み立てて話すこともできます。
【3歳から4歳】複文を使える
2つ以上の主語と述語から構成される文を複文といいます。3〜4歳頃になると、「おねつがあったから、ほいくえんはおやすみしました」という副文が使えるようになります。複雑な文法構造を理解し、日常的な言葉のやり取りができるようになってきます。
【4歳から5歳】話す意欲が高まる
語彙がさらに増え、複雑な文や長い文章を話す力がつきます。友達や仲の良いグループで話して遊び、自分の気持ちや感情を言葉で表現することも増えます。
以上のことは、あくまでも目安であり、子どもごとに個性や成長ペースがあるため、当てはまらないからと言って過度に心配する必要はありません。子どもごとの興味や個性に合ったコミュニケーションを行うことが、言葉の発達につながります。
なぜ言葉の発達が遅れるのか
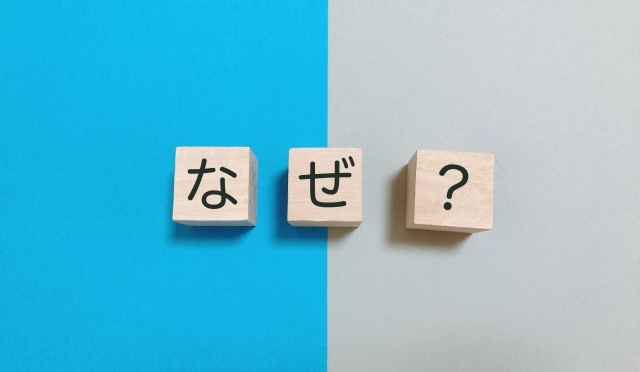
子どもの言葉の発達が遅くなる原因は多岐にわたり一つの原因だけで説明することはできませんが、
一般的には
- 個性や性格
- 単純性言語遅滞
- 聴覚障害
- 発達障害
などが考えられます。
それぞれを順に解説していきます。
個性や性格
子どもの個性や性格により、言葉が少なかったり発しない場合があります。特に内向的な性格の子どもは言葉を積極的に発しない事があります。
単純性言語遅滞
子どもの成長において、言語の発達だけ遅れることがあります。これを単純性言語遅滞といい、2〜3歳にかけて言葉が急激に発達します。もし、心配なようであれば定期検診などで相談してみると良いでしょう。
聴覚障害
聴覚障害がある場合、言葉が聞こえておらず言葉を発することができない場合があります。聴覚に問題があるかどうか、音を鳴らして反応があるか試してみましょう。
発達障害
自閉スペクトラム症スペクトラム障害(ASD)などの発達障害を持つ子どもは、言葉の発達にも影響が出ることがあります。
障害を持っていた場合は、定期検診の際に指摘されることが多く、専門機関で検査を行い診断されます。日常生活で気になる事があれば、定期検診で相談してみるのも良いでしょう。
子どもの言葉の発達のために「やってほしいこと」「さけたほうがいいこと」

最後に、子どもの言葉の発達をのために「やってほしいこと」と「避けたほうがいいこと」をいくつかご紹介します。
子どもの言葉の発達をのためにやってほしいこと
- 医師に相談する
- 記録する(例として、「活発な姉とだけ話をしている」「家に子ども以外、だれもいないので、誰とも話をしない」「子どもに話しかけているか」など(※「叱る」「指示をだす」は、話しかけていることになりません))
- 家で楽しい遊びをする
- 答えをどんどん言ってあげる (例として、「これは何かな?」「あ、すずめだね!」など)
子どもの言葉の発達をのために避けた方がいいこと
- むやみやたらに名前を呼ばないようにする。
- 質問する際にテストのようにならないようにする。(「これは何?」などしつこく聞かない)
以上の方法を参考に、できることから毎日の生活に取り入れてみてください。そうすることで子どもの言語発達を支援し、コミュニケーションスキルを育成することができます。
まとめ
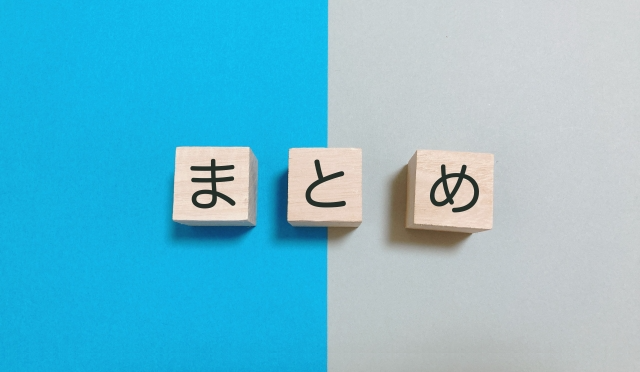
いかがでしたか。
親としては周りの子どもと比べてしまいがちですが、子どもの成長は十人十色です。
「そろそろ話し始めても良い頃なのにな」と思うこともあるかもしれませんが、子どものペースに合わせて見守るのも大切です。
今回お話しした言葉の発達のためにできる方法を参考にしつつ無理のない範囲で、できることから取り組んでいくことがおすすめです。
あまり心配し過ぎず育児は楽しんでいきましょう。
チルドレン・センターでは、ABA(応用行動分析学)に基づく専門的な支援を通じて、これまでに1,000人以上のお子さまと向き合ってきた実績があります。指導にあたるスタッフは全員、ABAの国際資格(BCBA-D®:協会認定行動分析士-博士、BCBA®:協会認定行動分析士、BCaBA®:協会認定準行動分析士、RBT®:登録行動テクニシャン)を有する専門家です。
もし、悩まれてることがあれば、私たちチルドレンセンターは、随時ご相談を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。