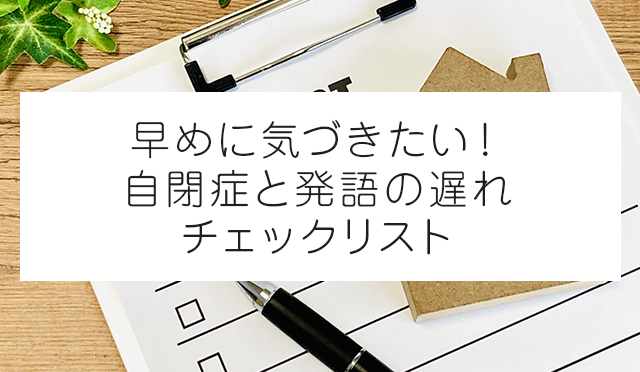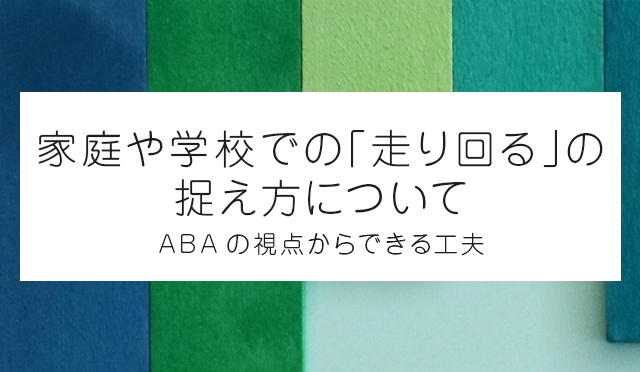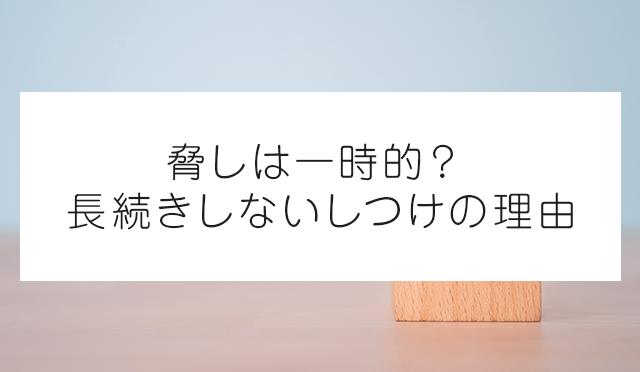子どもが走り回ってしまう理由と効果的な対応方法について
ファミレスなどで食事をしていて、子どもたちがわーーっと騒いで走っていたりすると、SNSで「最近の保護者は叱らない」などと書かれてしまうし、知らないおばさんが叱ったら今度はその保護者に、「チェ」と舌打ちされてしまうような世知辛い昨今です。
しかし、保護者の中には「こんなに叱っているのに」や「うちの子は何か変なんじゃないか」と思って「多動」「ADHD」「発達障がい」と検索する方もいると思います。このように、子どもが走り回ってしまうことに悩む保護者は多いです。
特に、発達障害(発達しょうがい)の可能性がある場合、その行動にどう対処すれば良いのか分からず、不安になることもあるでしょう。本記事では、子どもが走り回ってしまう理由をABA(応用行動分析学)の観点から理解し、効果的な対応方法を紹介します。
- 走り回ってしまうのはなぜか
- 走り回ってしまう特性のある発達障害(発達しょうがい)について
- 走り回ってしまう時の対応について(具体的な例)
走り回ってしまうのはなぜか?

日本の子どもたちは、基本的に「叱る」役をする人がいる前では、きちんと座ることができます。しかし、就学前の子どもが夏休みなど、家族だけでお出かけをする際には、食事の席や走ってはいけない場所でも走り回ることがあります。これは社会の中での子どもの位置づけだと個人的には思います。つまり「子どもだから仕方がない」と許される文化の中にいるからです。
例えば、欧州では子どもたちはレストランで走り回りませんし、レストランに子どもが来る機会もそれほど多くありません。
しかし、年齢が上がり子どもを「叱る」役の人がいる小学校に入学しても、他の子はきちんと座っているのに、自分の子どもは教室から飛び出してしまう場合があります。 そのため、「お家の方、一緒にいてください」と支援を要請する小学校もあると聞きました。
走り回ってしまう特性のある発達障害(発達しょうがい)について
子どもが走り回る行動は、発達障害(発達しょうがい(ASDやADHDなど))の一環であることがあります。これらの障害は、子どもの行動や注意力、感覚処理に影響を与え、結果として過度な活動や衝動的な行動が見られることがあります。ABAでは、「走り回る=発達障害(発達しょうがい)」と単純にみなすことはありません。 ABAでは、走る前に何をしていたのか、走り出したら何が起きるのかを分析します。
走り回ってしまう時の対応について(具体的な例)
家庭でできる工夫
今まで、何をしてきたか、記録をとってみる
いつも起きていることを記録してみます。 また、走りだす前に何をしていたかも同時に記録します。
例えば、
- 走ると「注意」はするが、聞かない。
- 10分後ぐらいにお父さんが抱っこして移動する。など
じっとしてくれているときに、きちんと賞賛をする。
タイミングを逃さず、じっとしているときにすぐに賞賛をするようにします。
専門家のサポート
発達障害(発達しょうがい)の疑いがある場合は、専門的な評価を受けることをおすすめします。 専門家による評価を受けることで、子どもの特性に応じた具体的な対策を教えてもらうことができます。
例えば、小学校で休み時間の終了のチャイムがなっても教室に戻ってこれない子どもがいます。このような場合、担任の先生や支援の先生が安全を確保するためにも呼びに行きます。
それでさらっと戻ってくれば問題ありませんが、小学校3年生になっても同じことを繰り返している場合、ABAでは、「走り回る」行動の機能(理由)を分析します。
その上で、介入の実践を行います。チャイムが鳴る前に(休み時間が終わる前に)支援者が何をするのか、休み時間が終わった後に本児が苦手な課題のときには課題の調整も必要になります。そして、実際に教室に戻すためには、誰がどのように動いて教室に戻すのかは、その行動の機能(理由)によります。
具体的な例として、苦手な算数の授業が3時間目にあったとします。児童は教室に戻らずに支援の先生と追いかけっこ(走り回る)方が、断然楽しいと感じます。これは発達に関係なく、通常でもそう思うことです。しかし、他の児童が教室に戻る中で、発達障害(発達しょうがい)の子どもが戻らないのは、「発達障害(発達しょうがい)だから仕方がない」のではないです。発発達障害(発達しょうがい)があるから走り回るのではなく、特定の先生が必死に追いかけてくれていたからという場合もあります。
この場合は、先生が良かれと思って実践したことが裏目に出てしまったのです。このような状況の介入にABAでは「教室に戻らない子は無視してください」と言うことがありますが乱暴に言っているのではありません。
この計画的無視※1は、本児の不適切行動の理由が「注目引き」の場合のみです。苦手な算数の授業があって走り回っているのに、無視をしても問題は解決しません。
※1 計画的無視とは問題行動を起こしている人を無視するのではなく、その特定行動だけを無視することです。
まとめ
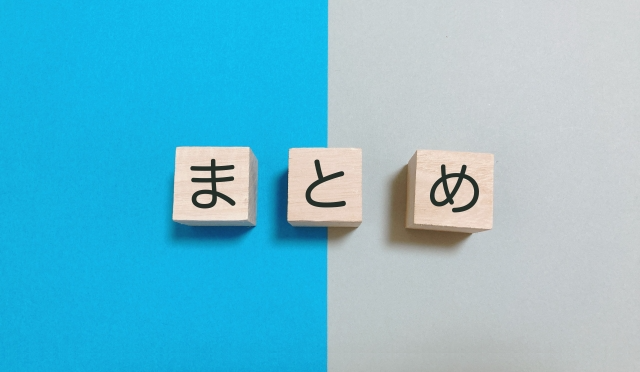
この記事では、子どもが走り回ってしまう理由と効果的な対応方法についてご説明いたしました。子どもが走り回ることに悩む保護者の一助となり、適切な対応を取るための参考になれば幸いです。
チルドレン・センターでは、ABA(応用行動分析学)に基づく専門的な支援を通じて、これまでに1,000人以上のお子さまと向き合ってきた実績があります。指導にあたるスタッフは全員、ABAの国際資格(BCBA-D®:協会認定行動分析士-博士、BCBA®:協会認定行動分析士、BCaBA®:協会認定準行動分析士、RBT®:登録行動テクニシャン)を有する専門家です。
気になることがあればお気軽にご相談ください。