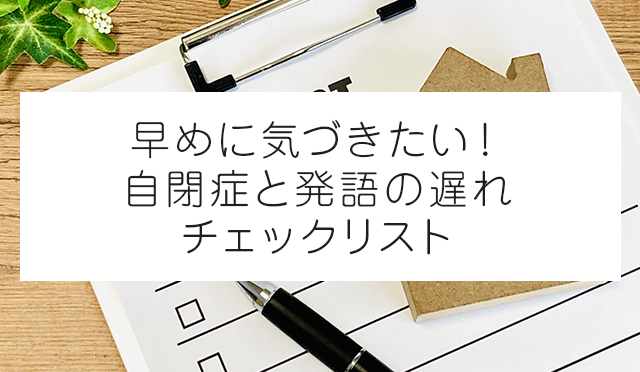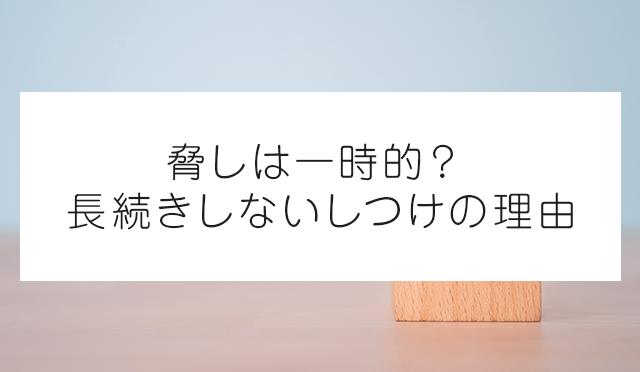家庭や学校での「走り回る」の捉え方について|ABAの視点からできる工夫
2学期に入ったと思ったら、残暑と行事とランダムに訪れるお休み(これはうれしいですが)に惑わされている毎日です。みなさんはいかがお過ごしでしょうか。
「2学期になってからも、子どもが落ち着かないんですよ」「いい夏休みをおくったはずなのに」「保護者にもお伝えはしているんですが…」など、公立の学校の先生方からご相談を受けます。
そして、保護者たちからは、「一学期もなかなか学校と連絡がとれなくて」「夏休みはリフレッシュして、家では問題ないんですけど」「今日も学校から電話がありまして」と、子どもの行動に困惑している学校や保護者は多いようです。
この記事では「走り回る」行動に関して、教室と家庭での対応をABA(応用行動分析学)の視点からご説明します。
- 子どもの「走り回る」の捉え方について
- 走り回る行動への具体的な対応方法
子どもの「走り回る」の捉え方について
そもそも「走り回ること」そのものが問題であるのか、という点から考えていくと、学校と保護者の双方の「ズレ」を理解でき、互いを責めずに済むと思います。
ABAでは、まず環境を確認します。
例えば、学校には知らないうちに「ルール」があります。これは社会のルールでもあるので、「教室では、走り回らない」ができないと「言葉がわからないのか」「保護者は何を教えているんだ」などの憤りを覚える教員も少なくないでしょう。
しかし、保護者は「うちでは走ったりしないのに」と不思議がる方も少なくないのです。つまり、あるケースでは、「学校の授業中のみ」「教室で走り回る」子どもも中にはいるようです。
また、保護者の中には「え、そうなのかな、気づかなかった」と、実際には子どもがどんなに動いていても、幼少のころからそうだったため、単に気づかない、ということも実は少なくありません。
もちろん、それらを「家庭のしつけが悪い」と保護者のせいにするのは簡単ですが、もしその「行動」を減らすには、と考えた場合、次の方法を検討することも効果的です。
ABAでは経緯を聞き取りをします
A: 1年生の時からずっと走り回っている(今、4年生)
B: 1年生のときにはなかったが、今、2年生で、走り回っている
AとBの状態では、対応や進め方、改善方法は全く異なります。
Aの場合
全ての場面(家庭、教科別クラス、担任先生の指導、それ以外の場面)でも、果たしてずっとそうなのかを確認する必要があります。
このAの場合、大事なことは、子どもは走り回っているけれど、学習を問題なく進めることができているのか、それとも、学習が進まないことも問題なのか、によっても、対策が変わります。
Aの場合、「家庭だけ」「学校だけ」で取り組んでも成功率は下がります。医療関係などの専門家とつなぐことも検討した方が解決が早い場合があります。しかしそれはすぐに診断や、薬で解決ということを示唆しているのではありません。優秀な子どもの中には、どこか動いていないとちょっと思考がしにくいタイプの方もいます。走り回ることを禁じる、ということよりも、どうすれば安全にかつその子が成長をするのか、という観点からも検討をすることが重要です。
問題はB、つまり、一定の時期には落ち着いていたが、いつしか走り回ることが多くなってきたケースです。
Bの場合
ABAでは、これは明らかに「学習した行動だろう」とみなす場合が多いです。
それは、「走り回ること」で、この子どもが得ている結果から推測していきます。実際のケースでは、FA(機能分析)という過程を踏んでから実際に解決策をご提案していきます。ここでは、仮に「子どもが経験した、走った後に何がおきたのか」から、推測していきます。
例えば、ある学校では「走り回る」と、先生、支援員、他児とで必死に止める場合があったとします。
ABAではこのような場合、「計画的無視」や、「指示を出して身体拘束で止める」というような指導が以前は多かったようです。私たちもやっていました。しかし現在の国際的かつ倫理的な観点からは、そのいずれも実施しないことになっています。特に、急に身体拘束で止めてしまうと、行動の機能(理由)が、注目引きである場合、この走り回る行動が増加する可能性も高くなります。また、熱心なご指導をなさっている先生方に「計画的無視」という用語で説明をすると、実際は、「無視しようとしたのですが、難しいこともありました」と、余計に行動を増加させる環境を作り出していることもあります。
走り回る行動への具体的な対応方法
その対象の子どもの行動がAなのかBなのかを知るだけでも、対策は立てやすくなります。
校門は施錠されているか、雨の日は滑らないか、行事で使った道具は安全な場所にあるか。家庭では、ぶつかってけがをしないように配慮できているか。こうした点を確認することが大切です。なお、走らないようにと障害物を置くと、かえってけがをしやすくなります。
先生方の中には、細やかに注意をしたいタイプの方もいれば、おおらかにとらえて注意を減らせるタイプの方もいます。そして、そのクラスの児童たちは先生の行動を模倣します。先輩の先生から助言を受けても、自分のクラス運営がうまくいかないと感じることがあるかもしれません。しかし、それは決して「だめな先生」や「下手な先生」ということではありません。指導方法や接し方の提案が、その先生自身の行動スタイルに合っていないだけなのです。
ここからは、本来であれば個別の計画を作成するために専門家に相談するとよいのですが、まずは管理職の先生方にも問題を共有し、「改善」のために1〜3までの記録を2週間ほど取ってみましょう。
その上で、細やかな先生であれば、ABAの観点から「先に賞賛をする」という方法をおすすめします。賞賛には技術が必要であり、それも合わせて練習していくと効果的です。
一方、比較的おおらかなタイプの先生であれば、「まず授業」ができるように先に安全対策を整えておくことが大切です。安全対策が整っていなければ、ABAで推奨される「計画的無視」の実践も難しくなります。
まとめ
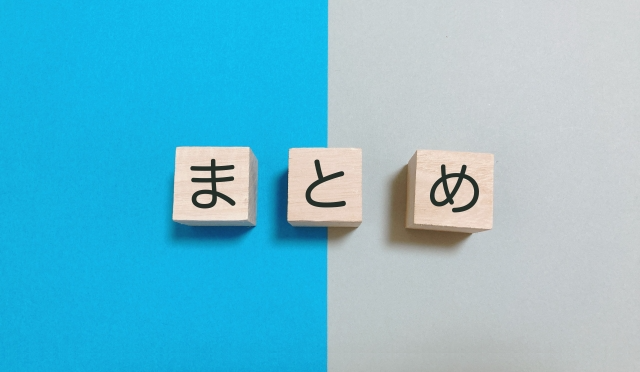
今回は簡単なご紹介でしたが、叱責や注意だけでは減らない子どもの行動への理解と対応のヒントになれば幸いです。
走り回ること自体は子どもの自然なエネルギーの表れです。しかし、日常生活や安全面で困りごとにつながる場合もあります。ABAでは「なぜその行動をしているのか?」を見極め、叱るのではなく、学べる環境を整えることを大切にしています。
チルドレン・センターでは、ABAの専門家が一人ひとりに合わせた支援を行っています。ご不安やお困りのことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。
チルドレン・センターでは、ABA(応用行動分析学)に基づく専門的な支援を通じて、これまでに1,000人以上のお子さまと向き合ってきた実績があります。指導にあたるスタッフは全員、ABAの国際資格(BCBA-D®:協会認定行動分析士-博士、BCBA®:協会認定行動分析士、BCaBA®:協会認定準行動分析士、RBT®:登録行動テクニシャン)を有する専門家です。