2〜3歳頃から子どもは活発さが増し、行動範囲も広がるので、好奇心のままに行動することがあります。
万が一子どもになにかあっては大変です。子どもの脱走は未然に防ぎたいもの。
今回は、「子どもが脱走してしまう理由」と「脱走する子どもの気持ち」、「脱走への対策」について解説していきます。
- 子どもが脱走してしまう理由
- 脱走する子どもの気持ちとは?
- 脱走への対策
できるだけわかりやすく、子どもが脱走してしまう理由と対策、脱走する子どもの気持ちについて解説していきます。
子どもが園や部屋を脱走してしまう理由

子どもが 脱走したり、離室したりするのはなぜでしょうか?
療育の環境で、脱走は英語でも「elopement」という行動として定義され、「最も危険」な問題行動として介入をいれるケースが多いです。
「脱走」や「離室」してしまう理由には次のことが一般的に考えられます。
初めての場所や興味のある場所を見てみたい!
新しい場所や環境は、見に行きたいのは当然だと思います。この場合、すべてを「脱走」と捉えなくても良いでしょう。
保護者が忙しい
例えば、「急に保護者に電話がかかってきた」「夫婦だけで会話をしている」や「他の兄弟で話をしている時間が多い」など、他の人とコミュニケーションをとることができな環境に置かれることによってその場から「脱走」してしまうことがあります。
ただただ部屋(家)から出てしまう
家の中、部屋の中を「ぐるぐる回る」「ずっとダッシュをしている」などの行動があるお子さんの場合で月齢相応のプレイスキルが低い場合は、機能的な理由が明確でなく、ただ単に部屋(家)を出てしまう場合も考えられます。
なぜ脱走をしてしまうのか(ABAの観点から)
ABAでは、なぜ「脱走」してしまうのかを、行動の機能を分けて分析をします。
例えば、
- 他の部屋に触りたいものがある:行動の機能(モノ)
- 保護者が忙しい、ほかの人と話している:行動機能(アテンション)
- ただ単に部屋からでていってしまう:自動強化
などです。

脱走への予防策

子どもの脱走には、子どもの個性や状況に合わせた適切な対応が求められます。子どもの安全を守るために保護者や先生が協力しあい、脱走の理由を理解した上で、予防策を検討することが大切です。
脱走ができないような環境を検討する
子どもの月齢に合わせて、危険を防止できるような環境を検討することも、大切です。
「すべてのドアを施錠する」という場合もあれば、「行動の機能」に合わせて対策を練ることが大切です。
記録をとる
どんな時に出て行ってしまい、誰が何を本児にしているのでしょうか?
例えば、
- 出て行ってしまったことに10分以上気が付かないで、警察を呼ぶことがあったのか?
- 出ていったら大人が大きな声をかけながら、走って捕まえに行くのか?
など、記録をとることによって状況を把握しやすくなり対策を練ることができます。(それぞれの場合によって予防策が違います)
外出前に写真をとる
「脱走」の危険が、外出時や新しい場面に多いときには、外出前に玄関で写真をとって携帯に送っておきましょう。「外出する時」「新しい場所に行く時」「新しいシッターさんや先生と会う時」など、その場面で記録(写真)を取っておくことによって、万が一、脱走した時に他者へ支援を求める際、役に立ちます。
デバイスを検討する
タイル(忘れ物防止タグ)など、紛失を防ぐためのデバイスを外出時にポケットに忍ばせておくのも予防策になります。ただし、本人が嫌がったり、引っかかる、落とすことへの対策と検討することが同時に必要になります。
まとめ
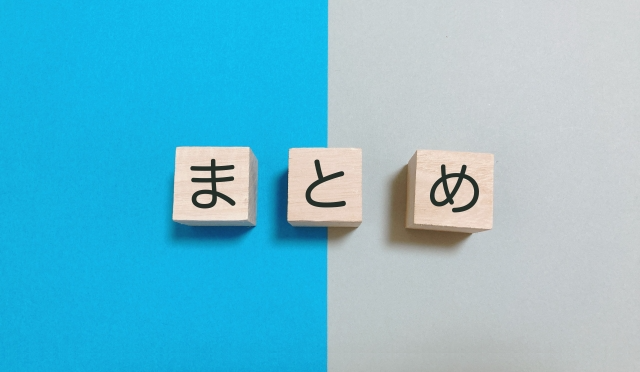
脱走や離室が続いてしまうと保護者は、「どうしてうちの子ばかり」「言葉がわからないからだろうか」、「知的に問題があるのか」と、落胆する方も多いと思います。
しかし、子どもであれば広い場所や新しい場所では大きな動きをしたくなるものだと思います。
単に脱走や離室させないために、物理的な「施錠をする」という対策だけではなく、
記録をとって行動の機能を予測したり、その行動の機能を正確に把握することによって、対策は立てられます。
チルドレン・センターでは、ABA(応用行動分析学)に基づく専門的な支援を通じて、これまでに1,000人以上のお子さまと向き合ってきた実績があります。指導にあたるスタッフは全員、ABAの国際資格(BCBA-D®:協会認定行動分析士-博士、BCBA®:協会認定行動分析士、BCaBA®:協会認定準行動分析士、RBT®:登録行動テクニシャン)を有する専門家です。
もし、3か月ほど、そのような行動が継続していて、様々な対策が効果的ではないと感じていることがあれば、ご気軽にご相談ください。









